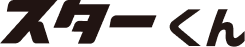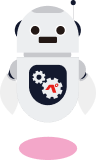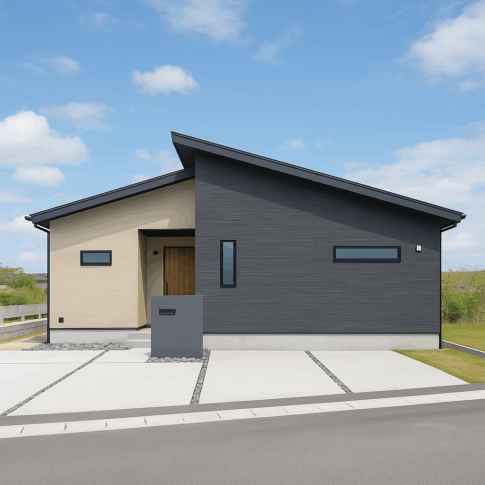築十数年を迎えたベランダに白い粉が付着したり、色あせが進んだりしていませんか。これはトップコートが寿命を迎え、防水層が紫外線に負け始めているサインです。そのまま放置するとコンクリートへ雨水が浸み込み、室内漏水や下階への損害につながります。とはいえ業者へ依頼すると十万円前後の出費……。「自分で塗れないだろうか」と検索する方が急増している理由はここにあります。本記事では年間3,000件以上の施工実績を誇るスターペイントが、DIYとプロ施工の判断基準、費用、塗料選び、手順、メンテナンス、トラブル対処まで徹底解説します。
DIY可否を3秒で判定!ベランダ防水セルフチェック
DIY向き/業者向きセルフチェックリスト
築年数・既存防水材・ひび割れ幅・雨漏り履歴・下地の浮き・シート防水の有無・排水勾配・直近の塗装歴――この八項目を○×で埋めるだけでご自宅のDIY適性が分かります。ひび割れが1 mm未満で既存がFRPまたはウレタン、防水層に雨染みが無い場合はトップコート再塗装だけで性能を取り戻せる軽症である場合が多いです。粉吹きだけなら洗浄+再塗りで済み、材料費も2万円前後に抑えられます。逆に○が3つ以下なら下地腐食や防水層剥離が進行している恐れが高く、表面だけ塗り替えても短命に終わります。診断の際はスマホで床面を接写し、拡大して細かなクラックや膨れを確認する方法が有効です。撮影した画像は作業記録として残せるほか、火災保険や専門業者へ相談するときの資料にも役立ちます。スターペイントでは初回無料診断時に同様の8項目メソッドを用いますが、現地では含水率計や赤外線温度計を併用して精度を高めています。こうしたプロのチェック手法を簡易化したのが本チャートなので、まずはセルフ判定で現状を把握し、DIYに進むかプロへ相談するかの分岐点を明確にしてみてください。
DIY向き/業者向き判定表
| # | チェック項目 | YES=DIY向き | NO=業者推奨 | 判定の目安・補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひび割れ幅が 1 mm 未満 である | ☑ | ☐ | 1 mm 以上なら雨水が浸入しやすく、補修材の充てんや下地補修が必要です。 |
| 2 | 既存防水が FRP か ウレタン である | ☑ | ☐ | シート防水やアスファルト防水の場合は専用工法が必要です。 |
| 3 | ベランダ床に 雨染み・漏水跡がない | ☑ | ☐ | 室内天井や外壁にシミがある場合は防水層の破断が疑われます。 |
| 4 | 床面に 膨れ・浮き・ペリペリ音 がない | ☑ | ☐ | 歩行時に浮き音が出るなら防水層が躯体と剝離しています。 |
| 5 | 排水口が詰まっておらず 勾配も確保されている | ☑ | ☐ | 水が 24 時間以上残る場合は勾配不良または詰まりを先に解消します。 |
| 6 | 下地が腐食していない(合板が軟化・黒ずみ無し) | ☑ | ☐ | 腐食が進むとトップコートだけでは持たず、張替えが必要です。 |
| 7 | 過去 5 年以内に シーリング打ち替え・大規模補修歴がない | ☑ | ☐ | 補修歴ありの場合、既存層との相性や密着が読めないためプロ診断推奨。 |
| 8 | 足場不要(1 階ベランダなど) で安全に作業できる | ☑ | ☐ | 2 階以上や高所作業が伴う場合は転落リスクが高く、業者が安全です。 |
○ が 6 〜 8 個 → DIY でトップコート再塗装が現実的です。
○ が 3 〜 5 個 → 軽補修+プロの簡易診断を受けたうえで判断しましょう。
○ が 0 〜 2 個 → 防水層や下地の劣化が進行している可能性が高く、専門業者への依頼を強くおすすめします。
プロに任せるべき4大症状
① 下地腐食
ベランダ床の合板やモルタルが黒ずんで軟らかくなっている状態です。内部まで水が浸透して木材や鉄筋が劣化している恐れがあり、トップコートを塗り替えても短期間で再剝離する可能性が高いです。下地補修や張り替えを含む専門工事が必要になります。
② シート防水の破断
ゴムシートや塩ビシートの継ぎ目が裂けて下地が露出している症状です。DIY でコーキングを充てんしても伸縮に追従できず再破断しやすいため、シート貼り替えや部分溶着などプロ専用の施工法が求められます。
③ 広範囲剥離
歩くと「ペリペリ」と音がする、または指で押すと塗膜が浮いて動く状態です。防水層全体が下地から離れているため、表面だけ再塗装しても密着力は回復しません。既存層を全面撤去してから新規防水を施工する大規模な作業が必要です。
④ 膨れ(ブリスター)
塗膜が袋状に盛り上がり、押すと中に空気や水分が感じられる症状です。防水層下に残った水分が温度変化で膨張することで発生します。膨れ部分を切開しても根本解決にならず、下地から湿気を抜いて再防水するプロセスが不可欠です。
いずれか一つでも該当する場合は、DIY では再発リスクが高く、費用もかさみやすいので、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。
費用徹底比較!DIYと業者のコスト&時間
DIYにかかる材料・道具・日数
三平方メートルのベランダをモデルに必要物資を算出すると、ウレタントップコート4 kg缶7,000円、プライマー1 kg2,500円、中毛ローラーと刷毛1,000円、マスカーやマスキングテープなど養生材1,500円、溶剤対応手袋とゴーグル500円、高圧洗浄機レンタル3,000円で合計15,500円に収まります。作業手順は①高圧洗浄1 h→②乾燥24 h→③養生0.5 h→④プライマー塗布0.5 h→⑤乾燥3 h→⑥中塗り1 h→⑦乾燥3 h→⑧上塗り1 h→⑨養生24 hです。気温が25℃前後なら2日で終わりますが、冬季や梅雨時は乾燥が遅れ3〜4日必要です。洗濯動線とペットの移動先を確保し、近隣に塗料臭の事前告知を行えばトラブルを防げます。スターペイントでは作業前に必ず「近隣挨拶カード」を配布し、作業時間・臭気・高圧洗浄の水跳ねについて周知していますので、DIYの場合も同様の配慮をおすすめします。
業者相場と保証価値
同じ面積を業者へ任せる場合、平均費用はおおむね12万円です。内訳は足場45,000円、高圧洗浄8,000円、防水工事50,000円、諸経費25,000円が目安となります。スターペイントでは工事完了後に最長10年の漏水保証書を発行し、3年ごとの無料点検を実施しています。点検ではドローン撮影と赤外線サーモグラフィで水分滞留を検出し、早期補修を提案します。万一漏水が発生した場合は無償で補修し、漏水に伴う内部造作の復旧費も独自の責任範囲でカバーする体制を整えています。DIYとの差額10万円は保証料と職人の技術料と考えられ、長期視点で見れば決して割高ではありません。特に二階以上のバルコニーは転落事故のリスクをゼロにできる点でもプロ施工の価値が高まります。
実際に、自分の家のベランダ防水の費用相場が気になる方はスターペイントが提供している費用シミュレーションサイトを使ってWEB上で簡単にチェックすることができます。
\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/
塗料&道具選び完全ガイド
トップコート3種比較
トップコートは防水層を守る最終保護膜で、ウレタン・FRPトップ・シリコンの三種類が主流です。ウレタンは伸縮性が高く施工温度の許容幅が5〜35℃と広く、初めてのDIYに適しています。FRPトップは硬膜で擦り傷に強く、既存がFRP防水なら相性抜群ですが、膜硬度が高いため下地クラックに追従しにくい欠点があります。シリコンは親水性により汚れが雨で流れ落ちやすく、光沢が長持ちする一方、価格はウレタンの1.3倍程度です。下記表で性能を比較し、既存防水種と期待耐用年数から選定しましょう。
| 種類 | 耐候年数 | 伸縮性 | 単価 | 施工難度 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン | 6〜10年 | ◎ | 低 | 低 | DIYの定番。迷ったらコレです。 |
| FRPトップ | 10〜13年 | ○ | 中 | 中 | FRP下地と合わせると高耐久です。 |
| シリコン | 8〜12年 | △ | 高 | 中 | 美観重視。セルフクリーニング性が魅力です。 |
スターペイントが戸建てで最も採用しているのはJIS A 6021適合ウレタンで、コストと耐久性のバランスが良く、調色も容易で景観に合わせやすい点が評価されています。
おすすめセットと容量早見表
ホームセンターや通販で入手しやすいエスケー化研「SKトップクリーンウレタン」とオート化学「オートンウレアックスHG」は、1 kg缶から20 kg缶までラインナップされ狭小ベランダでも余らせにくいです。容量目安は3 ㎡→4 kg、6 ㎡→8 kg、10 ㎡→12 kgが基本で、プライマーはトップコート量の25%を見込むと不足しません。ローラーは13 mmの中毛を選ぶと塗料含みがよく、アルミトレーは溶剤で変形せず再利用可能です。撹拌棒で5分以上しっかり混ぜることで顔料沈殿を防ぎ、色ムラを抑えられます。マスキングテープは耐溶剤タイプを使用し、塗装後24時間以内に45°でゆっくり剥がすと糊残りが少なく、エッジが美しく仕上がります。スターペイントでは現場残り塗料をOB顧客へ小分け販売するサービスも行っており、プロ仕様塗料を試したい方は問い合わせるとお得に入手できます。
プロが教える5ステップ施工マニュアル
ステップ1 高圧洗浄で旧塗膜と汚れを一掃する
ベランダ防水の成功可否は最初の高圧洗浄に大きく左右されます。洗浄圧は150 kgf/㎠を目安にし、デッキブラシでこする力の約20倍の洗浄力で旧トップコートの粉化層や黒カビ、排気ガスの油膜を一気に除去します。ノズルはトルネードタイプを使うと水流が螺旋を描き、細部に入り込んだ汚れまで削り落とせるため効果的です。手順は、まず排水口をビニール袋とゴムバンドで仮封鎖し、洗い流した汚れが排水管内で詰まらないようにします。次に壁際から中央へ向けて一定距離を保ち、ジグザグに噴射していきます。ノズル先端をコンクリート面に近づけすぎると素地を削りすぎたり、既存防水層を傷めたりする恐れがあるため、15〜20 cmをキープしましょう。最後に排水口の封鎖を外して大量の水で再度すすぎ、残留汚れを完全に流しきって初日の作業は終了です。スターペイントの現場では洗浄後にpH試験紙を当て、アルカリ成分が残っていないかを確認しています。DIYでも普及品のリトマス紙を使えば同様のチェックが可能で、乾燥後の付着不良リスクを格段に下げられます。
ステップ2 24時間乾燥と目荒らしで密着力を底上げする
洗浄直後のコンクリートやモルタルには想像以上に水分が残っています。乾燥不足のまま塗布すると塗膜内部に水蒸気が閉じ込められ、膨れや白濁が発生しやすくなるため、24時間以上は自然乾燥させることが鉄則です。冬季や梅雨時など湿度が高い期間は送風機を2台対角配置し、空気を循環させると乾燥速度が1.3倍に向上します。含水率計をお持ちでない場合は、床面に50 cm角のポリシートを養生テープで密着させ、3時間後に裏面へ曇りが出ないかを確認する簡易テストが有効です。完全乾燥を確認したら#120〜150のサンドペーパーで表面を満遍なく研磨し、細かな傷を付けて「アンカー効果」を高めます。研磨粉は塵取りとほうきで回収し、最後にエアダスターやブロワで微粉を吹き飛ばすとプライマーの食い付きが大幅に向上します。スターペイントでは研磨後に赤外線温度計で床温を測定し、10℃以上あることを確認してから次工程へ進むよう社内基準を設けています。
ステップ3 プライマーを0.12 kg/㎡で薄く均一に塗布する
プライマーは防水塗料と下地を化学的に接着させる接着剤の役割を担います。希釈済み一液タイプを使用する場合でも、缶底に固形分が沈殿しているため電動ミキサーで2分以上撹拌してから使用してください。塗布量は0.12 kg/㎡が標準で、ローラーは短毛6 mmを選ぶと塗り過ぎを防げます。塗り方は壁際から中央へ向かい、縦→横とクロスさせながら薄い膜を作るイメージで転がします。プライマーが溜まりやすい端部やパラペットとの取合いは、先に刷毛でダメ込みしておくとローラー跡が残らず仕上がりがきれいです。塗布後は指で触れてもべたつかない「指触乾燥」を確認し、さらに30分置いてから次工程へ進むと接着強度が安定します。気温5℃未満では硬化が遅れ、4時間以上たっても乾かないことがあるので、その場合は日を改める勇気も必要です。スターペイントでは硬化遅延リスクを避けるため、最低気温7℃以上の日程を工程計画の絶対条件にしています。
ステップ4 中塗り(主材)を0.25 kg/㎡で膜厚確保し気泡を抜く
中塗りは防水性能のコアとなる主材層を形成する工程です。塗布量は0.25 kg/㎡が目安で、膜厚不足はクラック追従性の低下や紫外線遮断性能の低下を招きます。作業時は中毛13 mmローラーに塗料をたっぷり含ませ、一方向に押し付けず軽く転がすことで気泡の巻き込みを抑制できます。それでも気泡が残った場合は、泡切りローラーで表面を軽く転がすと抜けやすく、乾燥後のピンホールを防止できます。中塗り後の乾燥時間は3時間が目安ですが、湿度70%以上の環境では4〜5時間へ延長してください。乾燥過程で埃が付着すると最終表面にブツが残るので、作業終了後はベランダ出入りを極力控え、室内からも窓を閉めて気流を遮断すると仕上がり品質が向上します。スターペイント現場では乾燥中に簡易テントを張り、落ち葉や虫の混入を物理的に防ぐケースもあります。
ステップ5 トップコート&乾燥養生で紫外線から長期保護する
上塗りとなるトップコートは紫外線や雨水から主材層を守る最前線です。塗布量は中塗りと同じ0.25 kg/㎡を確保し、クロス塗りで筋を完全に消します。希釈はメーカー指定溶剤を1〜3%以内に抑え、粘度が高いと感じても安易にシンナーを増やさないでください。過剰希釈は顔料沈殿を促し、色ムラや艶ムラの原因になります。塗布後24時間は歩行禁止とし、完全硬化までは約10日を要します。この間は重量物の設置や高圧洗浄を避け、ペットや小さなお子さまがベランダに出ないよう養生ネットを張って安全を確保しましょう。夏季は直射日光で表面温度が40℃を超えると膜が急速に硬化し脆くなるため、遮熱シートで日陰を作るとベストです。スターペイントでは上塗り翌日に光沢計で艶度を測定し、90グロス以上を合格基準に設定しています。DIYでも目視で均一な艶が確認できれば成功率は高く、コインで軽くこすっても色移りしない状態になれば養生撤去のタイミングです。
施工後10年守る!メンテナンスと再塗装サイクル
劣化サインと点検方法
半年ごとに行う点検では、まず手で撫でて粉が付くチョーキングを確認します。粉量が増えたらトップコートの樹脂が紫外線で分解し始めた証拠なので、再塗装を検討しましょう。次に全体を斜めから見て色あせをチェックし、光沢が均一に失われているか観察します。部分的に膨れている箇所は内部水蒸気の滞留が疑われるため、小さなカッターで切り込みを入れて水分を排出し、乾燥後に部分補修すると進行を抑えられます。最後に排水口回りの水はけを確認し、雨後24時間たっても水たまりが残る場合は排水口詰まりや勾配不良が発生しています。以上のチェックを写真で記録しておくと変化が追跡しやすく、補修時期の判断材料になります。
スターペイントのアフターケアサービス
スターペイントでは施工後3年ごとに無料点検を実施し、ドローンと赤外線サーモグラフィで躯体の水分滞留を調査します。報告書は写真と数値付きでメール共有し、劣化進行度を可視化します。DIY施工物件向けには防水ドック(9,800円~)を提供し、同様の検査を行います。さらに火災保険を用いた修繕サポートも行い、漏水損害が発生した場合は書類作成から保険会社との折衝まで一括代行します。過去には最大100万円まで自己負担ゼロで復旧した例もあり、施工後の安心をバックアップする体制が整っています。
Q&Aで即解決!トラブル対処と保険活用
よくあるトラブルの原因と応急策
乾かないときは床面温度が5℃未満か湿度が85%以上であるのが主原因です。ヒートガンで局所加温し、送風機で換気すれば硬化が進みます。色ムラは撹拌不足か塗布量不足です。塗料を5分以上攪拌し、上塗りを0.15 kg/㎡で薄く全体に重ねると改善します。気泡はローラー速度が速すぎる場合に起こるため、1秒に60 cm以下を目安にゆっくり転がします。剥離が局部的に起きたらサンドペーパー#80で周囲を削り落とし、プライマーを再塗布してトップコートを2回重ねれば再密着します。
DIY後の保証・保険・プロ併用プラン
DIYはメーカー保証外ですが、火災保険の外部給排水設備補償が適用される場合があります。下階への漏水シミが出た際、復旧費用が全額補償される例も少なくありません。申請には工程写真と原因報告書が必要なので、作業中はスマホで細かく撮影しましょう。3年後にプロ再塗装へ切り替える場合、下地が健全なら保証期間を延ばせるため、DIY+プロ点検のハイブリッド運用がコストと安心の両立策です。スターペイントでは保険申請代行も行い、自己負担ゼロで復旧した実績が多数あります。
ベランダ防水をDIYでおこなう場合のメリットとデメリット
メリット① 材料費だけで 10 万円近く節約できる
DIY 最大の恩恵は、なんと言っても費用を大幅に抑えられる点です。一般的なベランダ(3〜6 ㎡)を業者に依頼すると、足場・高圧洗浄・防水材・人件費・諸経費を合わせて 10 万円前後が相場になります。一方、DIY ならウレタントップコートとプライマーで 1〜2 万円、道具や養生材を加えても合計 2 万円程度に収まります。浮いた 8〜9 万円は、外壁や屋根の貯蓄リフォーム資金、あるいは家族旅行など別の目的に充当できるため家計インパクトが大きいです。ホームセンターや EC サイトのポイント還元を活用すれば、実質負担をさらに下げることも可能です。近年は DIY ブームの高まりを受け、プロ仕様の塗料が 1 kg 単位で購入できるストアも増えています。スターペイントでも「材料だけ分けてもらえますか?」という OB 客の声に応え、余剰在庫を小分け販売するサービスを提供しており、信頼できる製品を割安で入手できるチャンスが広がっています。材料費の節約はもちろん、作業工程を自分のペースで管理できることで追加の人件費が不要になる点も見逃せません。うまく活用すれば、ベランダ防水にかけていた想定予算を丸ごと別のリフォームや趣味に振り向けることができ、生活の満足度を高められる大きなメリットにつながります。
メリット② 自分のスケジュールとこだわりに合わせて施工できる
DIY であれば作業日程を天気と家族の予定に合わせて自由に組めます。たとえば「春の大型連休に家族総出で取り組み、思い出と節約を同時に手に入れる」「梅雨入り前の晴れ間を狙って一気に仕上げる」といった柔軟なプランが可能です。色や質感も完全に自分好みに選べ、遮熱顔料入りやマット仕上げ、ラメ入りトップコートなど個性的な製品を使用してベランダをガーデンテラス風に演出できます。施工途中で「ここだけ色を変えてアクセントにしよう」「立ち上がりは二度塗りにして耐久性を上げよう」と思い立った変更も即座に実行できる点は、工程が事前に確定している業者施工では得がたいメリットです。SNS で進捗を発信して同じ趣味の仲間と交流したり、作業動画を残して家族の記録にしたりする楽しみもあります。スターペイントの色彩設計担当者は、こうした DIY 施工で生まれたユニークな配色事例を参考に外壁カラープランを提案することもあり、創意工夫が住まい全体のデザイン向上につながる好循環が生まれています。
メリット③ 住まいへの愛着が深まりメンテナンス意識が高まる
自分の手でベランダを塗装すると、床勾配や排水口形状、立ち上がりの取合いなど普段意識しない細部に目が届くようになります。「次は手すりを塗り直そう」「サッシ回りのシーリングも点検しよう」と住宅全体の保守に対するアンテナが鋭くなり、結果的に不具合の早期発見と長寿命化につながります。スターペイントが実施した OB アンケートでは、DIY 経験者の 83% が「家の異変に早く気づけるようになった」と回答しています。家族で協力して作業した場合は達成感が共有財産となり、完了後のベランダでバーベキューやガーデニングを楽しむことで“わが家時間”がいっそう充実します。自分で塗った塗膜には自然と愛着が湧き、多少の汚れや傷も定期的に手を入れて維持しようという気持ちが芽生えます。この心理的なリターンは金額換算しづらいものの、暮らし全体の満足度を大きく押し上げる重要なメリットと言えます。
デメリット① 施工ミスによる再工事で結局高くつくリスクがある
DIY の最大の落とし穴は、乾燥不足や塗布量不足、気泡混入などのミスが原因で数か月以内に剝離・白濁が発生し、再施工が必要になるリスクです。再工事では旧塗膜剝離や廃材処分費が上乗せされ、足場が絡めば 15〜20 万円かかるケースも珍しくありません。スターペイントのトラブル対応実績でも、DIY 失敗からの再依頼案件は年々増加しており、初回に業者へ任せていれば回避できたはずの費用が発生する例が数多く報告されています。特に目視では判断しづらい下地含水率や硬化温度管理はプロが計測機器で管理する領域で、ここを見誤ると想定以上のダメージが出やすいです。費用節約のつもりが結果的に高額になる「負のスパイラル」を避けるためにも、施工前に気象条件・乾燥時間・塗布量を厳守できるかを慎重に検討する必要があります。
デメリット② 安全・健康面のリスクと周囲への影響
二階以上のバルコニーは転落事故の危険が常に付きまといます。脚立がぐらついたり、塗料で足を滑らせたりして落下すれば大ケガにつながりかねません。また溶剤系塗料のシンナー臭は頭痛や吐き気を誘発し、肌に付着すれば皮膚炎を起こす恐れがあります。さらに塗料飛散が隣家の車や外壁に付くと賠償問題に発展するリスクもあります。スターペイントの現場では安全帯や防毒マスク、飛散防止ネットを必須装備とし、気温・風速・湿度の基準を超えた場合は作業を中止する厳格なルールを設けています。DIY でこれらをすべて揃えるとコスト増となり、「節約したはずが健康被害や近隣トラブルで出費が増えた」という本末転倒な結果になりがちです。作業前の近隣挨拶や風向きチェック、防護具の準備を怠ると心理的ストレスも高まり、DIY の楽しさが半減してしまいます。
デメリット③ 保証が得られず長期コストが読みにくい
業者施工なら 5〜10 年の漏水保証が付くのが一般的で、万一雨漏りが起きても無償補修を受けられます。DIY にはこうした保証がなく、3〜5 年で再塗装が必要になった場合も全額自己負担です。ベランダは日射条件や風当たりによる劣化速度の差が大きく、耐用年数を正確に予測しづらい部分でもあります。さらに火災保険の外部給排水設備補償を活用する場合、施工前後の写真や原因報告書の提出が必須で手続きが煩雑です。スターペイントでは DIY 物件向けに 3 年ごとの有料点検サービスを用意し早期異常を検出できますが、保証付き施工に比べると出費がかさむことは避けられません。「短期の節約」と「長期の安心」を天秤にかけたうえで、どこまで自己責任で管理できるかを冷静に判断する必要があります。
ベランダ防水をDIYで施工する際の注意点
施工前に確認すべき気象条件とスケジューリング
防水塗料は温度・湿度・風速に敏感です。気温が5℃未満では硬化反応が遅れ、湿度85%以上では表面が白濁しやすくなります。風速5 m/sを超えると塗料が飛散し、隣家や車に付着する恐れがあるため注意してください。天気予報を確認し、降水確率30%以下が48時間続くタイミングを選ぶと安心です。作業は午前9時に開始して15時までに上塗りを終えると夜露の影響を受けにくくなります。スケジュール表を作成し、乾燥時間を含めたタイムラインを可視化すると作業遅延を防げます。
安全対策と近隣トラブルを防ぐポイント
高所作業では滑りにくい靴とハーネスを着用し、工具落下防止ロープを使うと安全性が高まります。溶剤系塗料を使用するときは防毒マスクとゴーグルで揮発成分から身体を守りましょう。風向きを確認してブルーシートで飛散防止を徹底し、塗料が隣家の窓や車に付着する事故を防ぎます。作業前日に近隣へあいさつし、「臭いが出る作業を○時から○時まで行います」と周知すると苦情を避けられます。また、使用済みローラーや溶剤を排水口に流すと環境汚染の原因になるため、産廃ルールに沿って廃棄することも忘れないでください。
まとめ

ベランダ防水のトップコート再塗りは、正しい手順と環境条件を守れば2万円前後の材料費と2日間の作業で完了します。セルフチェックで劣化度合いを見極め、軽症ならDIY、重症ならプロ施工を選択することが成功への近道です。DIYの場合は下地乾燥と温湿度管理を徹底し、半年ごとの点検と排水口の清掃を習慣化すれば、防水性能を長期間維持できます。プロの定期点検や火災保険を併用すれば、コストを抑えながらも安心感を確保できます。本記事を参考に、最小出費で最大の安心を手に入れてください。
雨漏りしてからでは遅い!梅雨に入る前に解決!
これから梅雨に入ってくると、ベランダの雨風による影響はどんどん強まっていきます。雨漏りしてから、劣化してから工事をするとその分費用も上がってしまいます。無駄な費用が発生する前にもまずは無料点検を業者に依頼することをお勧めします。とりあえず費用だけでも知りたいという方は弊社の費用シミュレーションサイトを是非ご活用ください。お家の情報を入力するだけで簡単に費用相場を確認することができます。
\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/