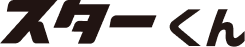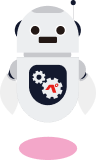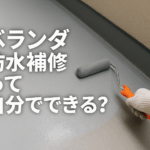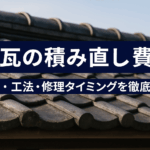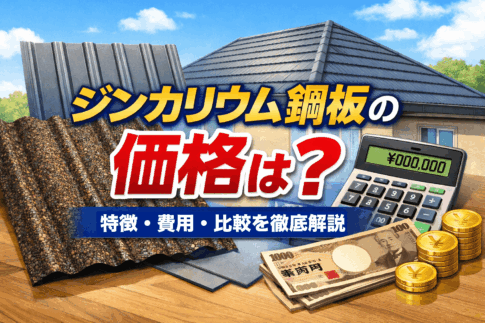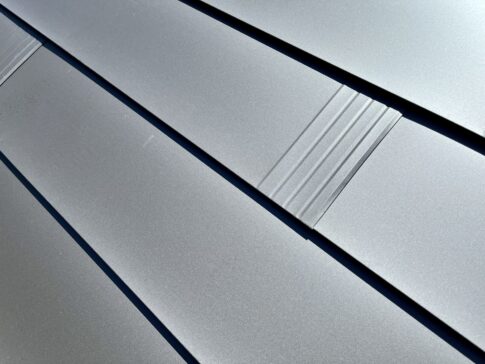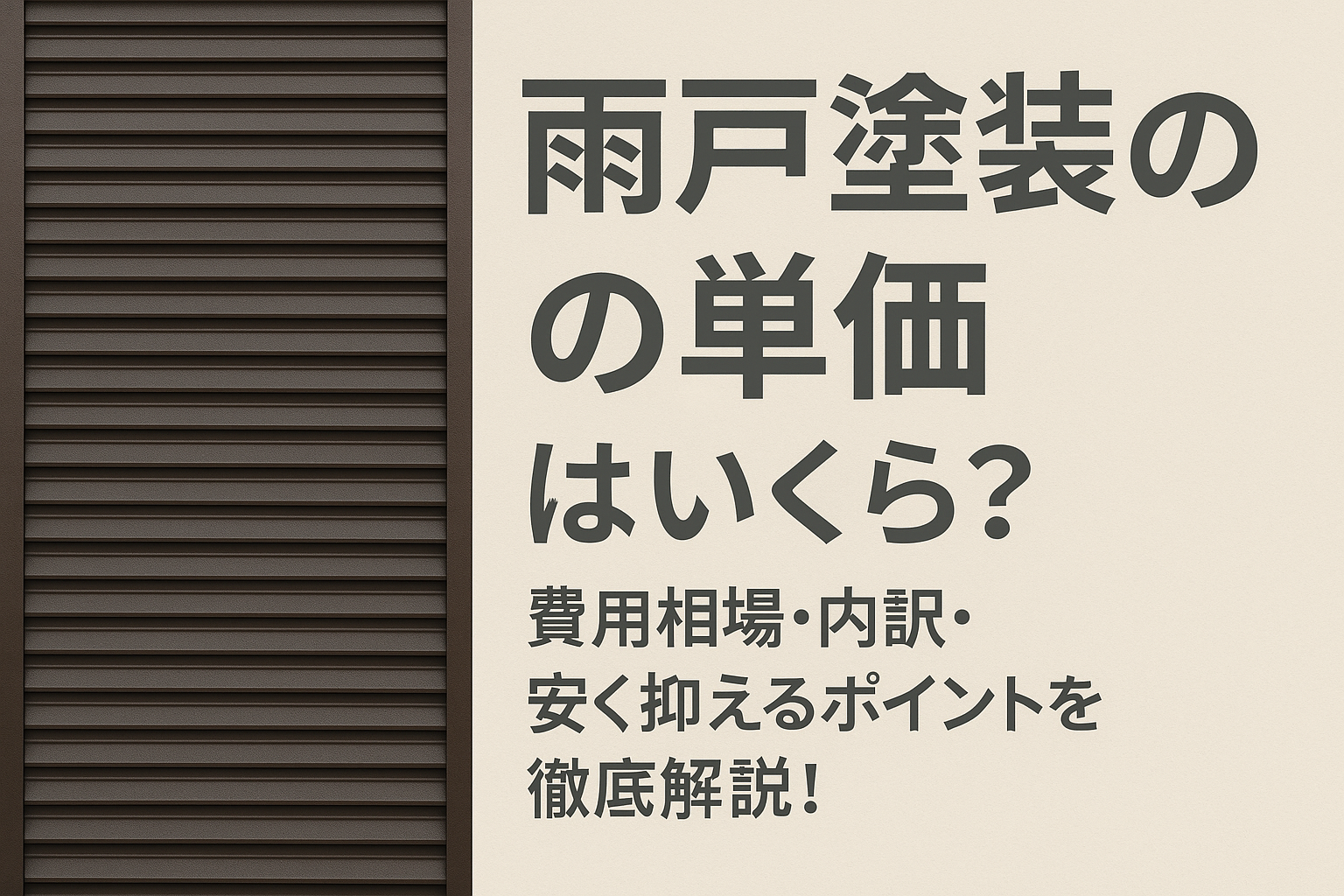
はじめに
ご自宅の雨戸、最後にメンテナンスしたのはいつでしょうか? 外壁や屋根の塗装に比べて、雨戸の塗装はつい後回しにされがちな部分です。しかし、雨戸は家の外観イメージを大きく左右するだけでなく、雨風や紫外線から窓を守るという重要な役割を担っています。
色あseやサビが目立つ雨戸をそのまま放置してしまうと、単に見た目が古びて見えるだけでなく、開閉がしづらくなったり、腐食が進んで穴が空いてしまったりと、機能面での問題にも直結します。最悪の場合、塗装では済まずに高額な交換費用が必要になるケースも少なくありません。
この記事では、雨戸塗装の「単価(1枚あたりの費用)」を中心に、プロの視点から費用相場、価格の内訳、雨戸の材質による単価の違い、適切な塗り替え時期、そして費用を賢く抑えるコツまで、徹底的に解説します。大切な住まいを長持ちさせるための知識として、ぜひ最後までご覧ください。
\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/
雨戸塗装の単価と費用相場を知ろう
概要文:まずは、雨戸塗装にかかる単価の基本相場を確認しておきましょう。雨戸1枚あたりいくらかかるのか、そしてその単価がどのような要因で決まるのかを詳しく解説します。
雨戸1枚あたりの塗装単価の目安
雨戸塗装の単価は、一般的なサイズ(掃き出し窓サイズ)で1枚あたり2,000円~5,000円前後が相場です。この価格には、下地処理(ケレン作業)から下塗り・中塗り・上塗りの3回塗りの工賃と塗料代が含まれます。
ただし、この単価はあくまで目安であり、依頼の仕方によって大きく変動します。
最も注目すべき点は、**「外壁塗装とセットで依頼するか、雨戸塗装単体で依頼するか」**という違いです。
もし、外壁塗装や屋根塗装といった大規模なリフォームと同時に雨戸塗装を依頼した場合、単価は1枚あたり2,000円~3,000円程度まで抑えられるケースがほとんどです。これは、塗装工事で最も大きなコストの一つである「足場の設置費用」を外壁塗装と共用できるためです。また、職人の移動費や準備の手間(養生など)も一度で済むため、効率が良く、単価を安く設定できるのです。
一方で、雨戸の塗装だけを単独で依頼すると、単価は1枚あたり4,000円~6,000円と割高になります。なぜなら、たとえ雨戸数枚の塗装であっても、職人が現地へ移動するための出張費や諸経費が発生するからです。さらに、もし2階部分の雨戸を塗装する必要があれば、そのために足場を組まなければならず、足場代だけで別途10万円~20万円の費用が上乗せされてしまいます。
雨戸塗装の単価を左右する主な要因は、以下の通りです。
- 枚数:枚数が多ければ多いほど、1枚あたりの単価は下がる傾向にあります。
- 形状:シンプルな一枚板のタイプか、可動式のルーバー(ガラリ)タイプか。凹凸が多いルーバータイプは、清掃や塗装の手間がかかるため単価が上がります。
- 素材:金属製(スチール)、アルミ製、木製など、素材によって下地処理の方法や使用する塗料が異なり、単価が変わります。
- 劣化状況:サビや古い塗膜の剥がれがひどい場合、下地処理(ケレン作業)に時間がかかるため、その分工賃が上乗せされます。
- 施工環境:1階の作業しやすい場所か、2階以上で足場が必要か。また、雨戸を取り外して作業場で塗装(吹き付け塗装)するか、取り付けたまま塗装(ハケ・ローラー塗装)するかによっても変わります。
これらの要素を踏まえた施工パターン別の単価目安を以下の表にまとめます。
| 施工パターン | 単価(1枚あたり) | 備考 |
| 外壁塗装と同時依頼 | 約2,000円 ~ 3,000円 | 足場を共用できるため、最もコストパフォーマンスが高い。 |
| 雨戸のみ単独依頼 | 約4,000円 ~ 6,000円 | 別途、出張費や諸経費がかかる。2階は足場代が必須。 |
| DIY塗装 | 約1,000円 ~ 2,000円(材料費) | 手間と時間がかかる。仕上がりの品質や耐久性に注意が必要。 |
費用内訳を理解する:塗装単価の構成要素
「雨戸塗装単価 3,000円」と聞いても、その内訳がどうなっているのか分かりにくいかもしれません。塗装工事の単価は、主に以下の5つの要素で構成されています。
- 下地処理(ケレン・清掃):古い塗膜やサビを研磨して落とし、塗料の密着性を高める作業。
- 養生作業:塗料が窓ガラスや壁、床などに飛び散らないよう、ビニールやテープで保護する作業。
- 塗料代:下塗り(錆止めなど)、中塗り、上塗りの3回分の塗料の費用。
- 塗装工賃:職人が作業(ハケ塗り、ローラー塗り、吹き付け)を行う手間代(人件費)。
- 足場費用(必要な場合):2階以上の作業で足場を設置する場合の費用。
これらの項目が、1枚あたりの単価にどのように含まれているのか、一般的な割合を以下の表に示します。
| 項目 | 内容 | 費用目安(1枚あたり) | 割合(目安) |
| 下地処理 | サビ落とし、高圧洗浄、ケレン(目荒らし) | 500円 ~ 1,000円 | 約20% |
| 養生・準備 | マスキングテープやビニールでの保護作業 | 200円 ~ 500円 | 約10% |
| 塗料代 | 下塗り・中塗り・上塗り(使用する塗料による) | 800円 ~ 2,000円 | 約30% |
| 施工工賃 | 職人の技術料・手間代(人件費) | 1,000円 ~ 2,000円 | 約30% |
| その他経費 | 足場代(共用)、機材運搬費、出張費など | 0円 ~ 500円 | 約10% |
※外壁塗装と同時依頼(足場代は外壁塗装に含まれる)の場合の目安です。
ここで特に重要なのが**「下地処理」と「養生」**です。
単価を安く見せかけるために、この下地処理(ケレン作業)を雑に行ったり、省略したりする業者がごく稀にいますが、絶対に避けなければなりません。サビや汚れが残ったまま塗装しても、新しい塗料はすぐに剥がれてしまい、数年もしないうちに再塗装が必要になります。また、養生が不十分だと、窓ガラスやサッシに塗料が付着し、見た目が非常に悪くなってしまいます。
また、**「塗料代」**も単価を左右します。塗料にはグレードがあり、一般的に以下の順で価格と耐久性が上がります。
- ウレタン塗料:安価だが耐用年数が短い(約5~7年)。
- シリコン塗料:コストと耐久性(約7~10年)のバランスが良く、現在主流。
- フッ素塗料:高価だが耐用年数が非常に長い(約12~15年)。
見積もりを見る際は、単に総額の安さだけでなく、どのグレードの塗料が使われ、下地処理がきちんと工程に含まれているかを確認することが、失敗しない塗装の鍵となります。
\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/
雨戸の素材によって単価が変わる理由
概要文:ご自宅の雨戸は何でできていますか? 雨戸には主に金属製(スチール・アルミ)と木製があり、その素材によって最適な塗装方法や使用する塗料が異なります。これが単価にも差が出る理由です。
金属製・アルミ製雨戸の単価と特徴
現在、日本の住宅で最も多く使われているのが金属製の雨戸です。主に「スチール(鋼板)製」と「アルミ製」に分けられます。
スチール(鋼板)製雨戸
- 特徴:比較的古い住宅に多く見られます。磁石が付くのが特徴です。
- 劣化症状:最大の敵は**「サビ」です。塗膜が劣化すると、そこから水分が浸入し、赤サビや茶サビが発生します。また、表面を手で触ると白い粉が付く「チョーキング現象」や、古い塗膜がパリパリと剥がれてくる**症状も出やすいです。
- 塗装のポイント:塗装前に「ケレン作業」と呼ばれる研磨作業を徹底的に行い、サビや古い塗膜を完全に除去することが不可欠です。この作業が甘いと、サビが再発し、塗膜が内側から持ち上がってきてしまいます。
- 使用塗料:下塗りにはサビの発生を抑える「エポキシ系錆止め塗料」を使用します。上塗りには、耐候性に優れた「シリコン塗料」または、さらに長持ちする「フッ素塗料」が推奨されます。
- 単価目安:1枚あたり 3,000円 ~ 5,000円
- メンテナンス周期:7~10年程度(シリコン塗料の場合)
アルミ製雨戸
- 特徴:近年の住宅で主流。軽量でサビにくいのが特徴です(磁石は付きません)。
- 劣化症状:アルミ自体はサビにくいですが、表面の塗膜はスチール製同様に劣化します。チョーキング現象や色あせが主なサインです。
- 塗装のポイント:アルミは塗料が非常に密着しにくい(付着しにくい)金属です。そのため、下地処理として表面に細かな傷をつける「目荒らし(ケレン)」をしっかり行い、アルミ専用の「プライマー(接着剤の役割を果たす下塗り材)」を使用する必要があります。
- 使用塗料:下塗りに専用プライマー、上塗りにシリコン塗料やフッ素塗料を使用します。
- 単価目安:1枚あたり 3,000円 ~ 5,000円
- メンテナンス周期:7~10年程度(シリコン塗料の場合)
金属製雨戸は、下地処理の質が耐久性に直結するため、単価が多少高くても、ケレン作業や錆止め工程をしっかり行う業者を選ぶことが重要です。
木製雨戸の単価と注意点
伝統的な日本家屋や、こだわりのある和モダン住宅では、今でも木製の雨戸(鏡板)が使われています。
- 特徴:木ならではの温かみと風合いが魅力ですが、金属に比べて水分や紫外線の影響を受けやすく、メンテナンスが非常に重要です。
- 劣化症状:水分を吸収・乾燥を繰り返すことで、木の**「割れ」「反り」が発生します。また、日当たりの良い場所では色あせ(日焼け)が、湿気の多い場所では「カビ」や「腐食」**が進みやすいです。
- 塗装のポイント:まず、割れや反りをパテなどで補修する作業(下地処理)に手間がかかります。金属製のケレンとは全く異なる技術が必要です。また、木材は塗料を吸い込むため、吸い込みを止めるための下塗り作業が重要です。
- 使用塗料:木材の呼吸を妨げない「浸透性塗料(木材保護塗料)」で木目を活かす方法と、塗膜を作って保護する「造膜タイプ(ウレタン塗料や油性塗料)」で仕上げる方法があります。腐食を防ぐために防腐・防カビ剤入りの塗料を選ぶのが一般的です。
- 単価目安:1枚あたり 4,000円 ~ 6,000円
- メンテナンス周期:5~8年程度(塗料による)
木製雨戸は、ヒノキやスギといった木材の種類によっても塗料の吸い込み方が異なります。下地処理や補修作業に時間がかかる分、金属製よりも単価が高くなる傾向があります。木製ならではの質感を保つためには、木の特性を熟知した経験豊富な業者に依頼するのが最善です。
塗装を行うタイミングと耐用年数
概要文:雨戸塗装は、どのタイミングで行うのが最適なのでしょうか。劣化のサインを見逃さず、適切な時期にメンテナンスを行うことが、雨戸本体を長持ちさせ、結果的にコストを抑えることに繋がります。
塗り替えのサインと見分け方
雨戸が「塗装してください」と発しているサインを見逃さないようにしましょう。ご自宅の雨戸をセルフチェックしてみてください。
- ① 色あせ・ツヤの消失【視覚的ポイント】:新築時や前回の塗装時と比べて、明らかに色が薄くなったり、くすんで見えたりします。特に南側や西側など、紫外線が強く当たる面の雨戸から劣化が始まります。これは塗膜の表面が劣化し始めた初期サインです。
- ② チョーキング現象(白い粉)【視覚的ポイント】:雨戸の表面を手で触ってみてください。手に白い粉(塗料の顔料)が付着する場合、これを「チョーキング現象」と呼びます。これは紫外線によって塗料の樹脂が分解され、防水機能が失われている明確な証拠です。
- ③ サビの発生(金属製の場合)【視覚的ポイント】:雨戸の端や、凹凸のあるルーバー部分、キズが付いた箇所から、赤茶色や黒ずんだサビが発生していないか確認します。小さな点状のサビ(点サビ)でも、放置すると内部で広がり、塗膜を押し上げてしまいます。
- ④ 塗膜の剥がれ・膨れ【視覚的ポイント】:塗装がパリパリと剥がれていたり、水ぶくれのようにプクッと膨れていたりする状態です。これは塗膜と下地(金属や木)の密着性が失われ、その隙間に水分が入り込んでいる証拠です。非常に危険な状態です。
- ⑤ 開閉時の重さ・異音【動作的ポイント】:雨戸を開け閉めする際に、以前より重く感じたり、「キーキー」「ガタガタ」といった異音がしたりする場合、戸車の劣化だけでなく、雨戸本体のサビや歪みが原因である可能性もあります。
これらのサインが1つでも見られたら、塗装メンテナンスを検討する時期です。
特に「サビ」や「塗膜の剥がれ」を放置すると、劣化が素材自体にまで進行し、サビで穴が空いたり、木が腐ってしまったりします。そうなると、もはや再塗装では対応できず、雨戸本体を交換することになり、1枚あたり数万円~十数万円という高額な費用がかかってしまいます。
\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/
塗装の耐久年数と再塗装の目安
雨戸塗装のメンテナンス周期は、使用する塗料の「耐用年数」によって決まります。耐用年数が長い塗料ほど価格は高くなりますが、塗り替えの回数を減らせるため、長期的なコスト(ライフサイクルコスト)は安くなる可能性があります。
| 塗料の種類 | 耐用年数(目安) | 特徴 |
| ウレタン塗料 | 5年 ~ 7年 | 比較的安価。以前は主流だったが、現在はシリコンに移行。ツヤがあり、細かい部分の塗装にも向く。 |
| シリコン塗料 | 7年 ~ 10年 | 耐久性・耐汚染性・価格のバランスが最も良い。現在の主流塗料。 |
| フッ素塗料 | 12年 ~ 15年 | 高価だが、耐久性・耐候性は最強クラス。長期間メンテナンスフリーを目指す場合に最適。 |
**再塗装の目安は、一般的に「7年~10年」**です。
これは、現在主流のシリコン塗料の耐用年数と一致します。
ここで最も重要なポイントは、**「外壁塗装のタイミングと合わせる」**ことです。
外壁塗装も、一般的にシリコン塗料が使われることが多く、その塗り替え目安も「10年ごと」と言われています。雨戸の劣化スピードも外壁とほぼ同じです。
どうせ10年後に外壁塗装で足場を組むのであれば、そのタイミングで雨戸も一緒に塗装してしまうのが、最も効率的で経済的です。前述の通り、足場代が共用できるため、雨戸塗装の単価を劇的に抑えることができます。「外壁が気になりだしたら、雨戸も一緒に」と覚えておきましょう。
DIYと業者依頼の違い・費用比較
概要文:雨戸塗装は、比較的手軽そうに見えるためDIY(自分で塗装)を検討する方もいらっしゃいます。DIYで雨戸を塗装する場合と、プロの業者に依頼する場合の違いを、費用・品質・安全性の面から具体的に比較します。
DIY塗装の費用・メリット・注意点
費用
DIYの場合、費用は塗料や道具代のみです。雨戸1枚あたりの材料費の目安は1,000円~2,000円程度でしょう。
(内訳:サンドペーパー、錆止め塗料、上塗り塗料、ハケ、ローラー、マスキングテープ、養生シートなど)
メリット
- コスト削減:最大のメリットは、工賃(人件費)がかからないため、費用を大幅に抑えられることです。
- 手軽さ:天気の良い休日に、自分のペースで作業を進めることができます。
デメリット(注意点)
- 仕上がりのムラ:スプレー塗装は風で塗料が飛び散りやすく、ハケやローラー塗りはムラやスジが出やすいです。特にルーバー(ガラリ)タイプの凹凸部分は、プロでないと均一に塗るのが難しいでしょう。
- 耐久性の低さ:最も差が出るのが下地処理です。プロが行うような徹底したケレン(サビ・旧塗膜の除去)は、専用の道具と技術が必要で、DIYでは不十分になりがちです。下地処理が甘いと、塗料がすぐに剥がれてしまい、結局「安物買いの銭失い」になる可能性が高いです。
- 安全性のリスク:1階の雨戸であっても、脚立からの転落リスクがあります。2階以上の雨戸を足場なしで塗装するのは絶対にやめてください。
- 塗料の飛散:養生が不十分だと、塗料が窓ガラスや外壁、車、さらにはお隣の家にまで飛散し、深刻なご近所トラブルに発展するケースがあります。
プロの工程との違い
DIYでは省略されがちなのが「下塗り(錆止め)」です。ホームセンターの塗料には「錆止め兼用」と書かれたものもありますが、プロは必ず「錆止め専用塗料」を塗布してから上塗りをします。この一手間が、5年後、10年後の耐久性に大きな差を生みます。
DIYでの塗装は、色あせが気になる程度の「軽度な劣化」で、なおかつ「1階部分」の作業に限定すべきでしょう。サビや塗膜の剥がれがすでに出ている場合は、プロに任せるのが賢明です。
業者依頼のメリットと失敗しない見積もりの取り方
業者依頼のメリット
プロの塗装業者に依頼するメリットは、DIYのデメリットの裏返しです。
- 高品質な仕上がり:ムラのない均一な塗膜で、新品同様の美しい仕上がりになります。
- 高い耐久性:素材と劣化状況に合わせた最適な下地処理と塗料を選定し、正しい工程(3回塗り)で施工するため、塗膜が長持ちします。
- 安全性と手間の削減:高所作業も安全に行い、面倒な養生や清掃もすべて任せられます。
- 保証:施工後に万が一不具合(塗膜の剥がれなど)が出た場合、保証期間内であれば無償で対応してもらえる安心感があります。
失敗しない見積もりの取り方
良い業者に依頼するためには、「見積書の比較(相見積もり)」が不可欠です。複数の業者から見積もりを取り、以下の項目を必ずチェックしてください。
【見積書チェック項目】
- 「一式」表記になっていないか?「雨戸塗装 一式 ○○円」という見積もりはNGです。「単価(1枚)× 枚数 = 合計金額」と明記されているか確認しましょう。
- 塗料名が具体的に記載されているか?「シリコン塗料」とだけ書かれている場合、どのメーカーの何という製品を使うのか分かりません。「日本ペイント ファインSi」など、メーカー名と製品名まで具体的に記載してもらいましょう。
- 工程が明記されているか?「下地処理(ケレン)」「下塗り(錆止め)」「中塗り」「上塗り」の**工程(最低3回塗り)**がきちんと含まれているか確認します。
- 保証の有無と期間雨戸のような付帯部(外壁・屋根以外の部分)にも保証が付くのか、付く場合は何年なのかを確認しましょう。
単価が安い業者に飛びつくのではなく、「なぜ安いのか」を考えることが重要です。塗料のグレードを落としていたり、工程を省いていたりする可能性はないか、見積書の内容をしっかり比較検討しましょう。
コツ
見積もりを依頼する際は、必ず**「外壁塗装とセットの場合の見積もり」と「雨戸塗装単体の場合の見積もり」**の2パターンをもらうと良いでしょう。その価格差を見れば、同時施工がいかにコストメリット(単価の安さ)があるかを実感できるはずです。
費用を抑えるためのポイント
概要文:雨戸塗装は必要なメンテナンスですが、できるだけ費用は賢く抑えたいものです。同じ塗装内容でも、依頼方法やタイミングを工夫するだけで、総額が大きく変わってきます。
外壁塗装と同時施工でコスト削減
雨戸塗装の費用を抑える最も効果的かつ王道の方法は、**「外壁塗装と同時に施工する」**ことです。これは本記事で何度も触れている最も重要なポイントです。
なぜなら、塗装工事の総額の約20%~30%を占めると言われる**「足場代」が、外壁塗装と雨戸塗装で共通化できる**からです。
例えば、雨戸塗装単体で足場を組むと15万円かかるところ、外壁塗装(足場代込み100万円)と同時に行えば、雨戸塗装のために追加でかかる足場代は「0円」です。
また、職人の人件費や移動費、養生作業などの「諸経費」もまとめることができます。
その結果、単独で依頼すれば1枚5,000円かかる塗装単価が、同時施工なら1枚2,000円~3,000円程度まで下がるのです。もし雨戸が10枚あれば、それだけで2~3万円も費用が浮く計算になります。
外壁塗装を行う際は、雨戸だけでなく、
- 雨樋(あまどい)
- 破風板(はふいた)・鼻隠し(はなかくし)
- 軒天(のきてん)
- 水切り(みずきり)
といった「付帯部(ふたいぶ)」も同時に塗装するのが一般的です。
これらの付帯部も、外壁と同じように紫外線や雨風にさらされて劣化します。足場があるこのタイミングで家全体を丸ごとメンテナンスすることが、美観を保ち、住まいの寿命を延ばすために最も合理的で、トータルコストを抑える最善策と言えます。
\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/
オフシーズンの依頼・地域相場の比較も有効
外壁塗装との同時施工以外にも、費用を抑えるためのいくつかの工夫があります。
1. オフシーズン(閑散期)を狙う
塗装業界には繁忙期と閑散期があります。
- 繁忙期:春(3月~5月)と秋(9月~11月)→気候が安定しており、塗装工事の依頼が集中する。
- 閑散期:夏(7月~8月)と冬(12月~2月)→梅雨や猛暑、積雪などで作業が制限されるため、依頼が減る傾向にある。
塗装業者も仕事が少ない閑散期には、価格交渉に応じてくれやすかったり、「閑散期割引キャンペーン」を行っていたりすることがあります。もし工事時期を急がないのであれば、あえて夏や冬に見積もりを依頼してみるのも一つの手です。(ただし、雨戸塗装単体での割引効果は限定的です)
2. 地域相場の比較
塗装費用には地域差があります。一般的に、人件費や地価が高い都市部(東京、大阪など)は単価が高くなる傾向があり、地方は安くなる傾向があります。ご自身の地域の相場感を把握することも大切です。
3. 施工店の形態(直営か下請けか)
塗装をどこに依頼するかも単価に影響します。
- ハウスメーカー、大手リフォーム会社:窓口となり、実際の工事は下請けの塗装店が行うことが多い。中間マージンが発生するため、単価は高めになるが、ブランドとしての安心感がある。
- 地域の塗装専門店(自社施工):自社の職人が直接施工するため、中間マージンがなく、単価を抑えられる傾向にある。技術力や対応は会社によって差があるため、見極めが必要。
中間マージンを省ける「地域の塗装専門店(自社施工店)」に直接依頼する方が、コストパフォーマンスは高くなる可能性があります。
雨戸塗装の施工工程と工期
概要文:プロの業者が行う雨戸塗装は、どのような流れで進められるのでしょうか。具体的な施工工程を知ることで、見積書に書かれている「下塗り」「ケレン」といった専門用語の意味を理解しやすくなります。
標準的な塗装の流れ
雨戸塗装は、単に色を塗るだけではありません。塗料の性能を100%引き出し、長持ちさせるために、以下のような緻密な工程を踏んで行われます。
1. 養生・清掃
まず、塗料が飛散してはいけない窓ガラスやサッシ、周辺の外壁などを、マスキングテープや専用のビニールシート(マスカー)で丁寧に覆います。その後、雨戸表面のホコリや汚れを清掃します。
2. ケレン(下地処理)
塗装工程で最も重要な作業です。サンドペーパー(紙やすり)やワイヤーブラシ、皮スキ(ヘラ)といった道具を使って、古い塗膜やサビを徹底的に擦り落とします。また、サビていなくても、表面にわざと細かい傷をつける「目荒らし」を行い、塗料の食いつき(密着性)を良くします。
3. 下塗り(錆止め)
ケレンで綺麗になった下地に、下塗り専用の塗料を塗布します。金属製雨戸の場合は「錆止め塗料」を塗り、サビの再発を防ぎます。アルミ製や木製の場合は、上塗り塗料との密着性を高める「プライマー」や「シーラー」と呼ばれる下塗り材を塗ります。この工程を省くと、早期剥離の最大の原因となります。
4. 中塗り
下塗りが十分に乾燥したら、仕上げ用の塗料(シリコンやフッ素など)を塗っていきます。これが1回目の上塗りです。中塗りの目的は、塗膜に十分な厚み(膜厚)を持たせることと、上塗り(仕上げ)の色ムラを防ぐことです。
5. 上塗り(仕上げ)
中塗りが乾燥したら、同じ仕上げ用塗料をもう一度重ね塗りします。これが仕上げの上塗りです。同じ塗料を2回塗ることで、塗料が持つ本来の耐候性や美観が発揮されます。
6. 乾燥・仕上げ
上塗りが乾燥したら、養生シートを剥がし、周辺に塗料が付着していないかなどを確認して完成です。
1枚の雨戸を仕上げるのに、これだけの工程と、各工程間での乾燥時間が必要になります。
工期の目安と注意点
工期(作業日数)の目安
雨戸塗装の工期は、枚数や天候、施工方法(取り外すか否か)によって変わります。
- 目安:雨戸10枚程度で、1日~2日
外壁塗装と同時に行う場合、外壁の塗装スケジュール(全体で約10日~14日)の中で、下地処理の日と中塗り・上塗りの日に組み込まれて進められます。
注意点:乾燥時間
塗装工事は「乾燥」が命です。
下塗り、中塗り、上塗りの各工程で、塗料メーカーが指定する乾燥時間(インターバル)を必ず守る必要があります。この乾燥が不十分なまま次の塗料を重ねると、塗膜の内部が生乾き状態になり、縮みや膨れ、早期の剥がれを引き起こします。
- よくあるトラブル例:塗装が完了した翌日、まだ塗膜が完全に硬化していないのに雨戸を動かしてしまい、雨戸と戸袋(収納部分)がくっついて塗膜が剥がれてしまった。
塗装が完了した後も、完全に硬化するまでは(特に夏場で24時間、冬場で48時間程度)、開閉は慎重に行うか、触らないように指示があるはずです。職人の指示に必ず従ってください。
まとめ
この記事では、雨戸塗装の単価を中心に、費用相場からメンテナンスのタイミング、業者選びのコツまで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを整理してまとめます。
- 単価相場雨戸塗装の単価は、1枚あたり2,000円~5,000円が目安です。ただし、これは依頼の仕方によって大きく変動します。
- 変動要因単価は、雨戸の素材(金属製か木製か)、劣化状況(サビや剥がれの程度)、形状(ルーバータイプか)によって変わります。木製や劣化がひどいものほど、下地処理の手間がかかるため単価は高くなります。
- 最もお得な方法費用を最も賢く抑える方法は、**「外壁塗装と同時に依頼する」**ことです。足場代や諸経費を共通化できるため、単独で依頼するよりも1枚あたりの単価を劇的に安く抑えることができます(例:1枚2,000円~3,000円程度)。
- メンテナンスのタイミング「色あせ」「チョーキング(白い粉)」「サビ」「塗膜の剥がれ」が見られたら、塗り替えのサインです。放置すると交換が必要になり、高額な費用がかかります。外壁塗装の目安である**「10年ごと」**に、雨戸も一緒に点検・塗装するのが最適です。
- DIYと業者の違いDIYは材料費(1枚1,000円~2,000円)のみで安価ですが、下地処理が不十分になりがちで、耐久性や仕上がりに大きな差が出ます。サビや剥がれがある場合は、プロの業者に任せることを強く推奨します。
- 見積もりのチェックポイント業者から見積もりを取る際は、単価の安さだけでなく、「塗料のメーカー名・製品名」「施工工程(3回塗り)」「保証の有無」が具体的に記載されているかを必ず確認してください。
雨戸は、住まいの美観を保つと同時に、厳しい自然環境から窓を守る防具の役割も果たしています。適切なタイミングで適切なメンテナンスを行うことが、雨戸本体、ひいては住まい全体の寿命を延ばすことにつながります。
最後に
11月は冬前の塗装の乾燥作業に最適な季節です。
スターペイントでは、3分のチャット入力で簡単に無料見積シミュレーションが可能です。
雨戸や外壁の塗装費用をすぐに把握できるので、ぜひお気軽にお試しください。
\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/